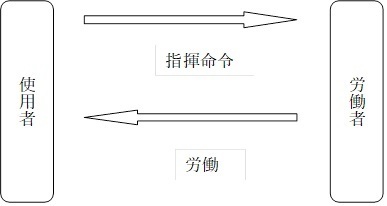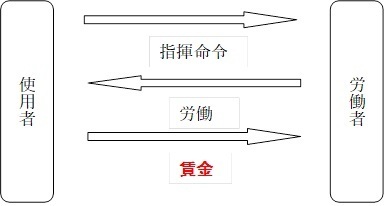これによると、平均賃金の計算方法は、次の通りとなります。
算定事由発生日以前3箇月間の賃金総額÷その期間の総日数
【賃金総額について】
賃金総額は、「総額」というぐらいですから、手当も全部含めます(住宅手当、通勤手当などもです。これらを除いて良いのは割増賃金の単価ですので、お間違いなく。)。ただし、次のものは除きます。
〇 期間・賃金共に除外
・業務災害による病気やケガの治療のための休業期間中
・産前産後休業期間
・使用者の責に帰すべき休業期間
・育児・介護休業期間
・試用期間
〇 賃金総額のみ除外
・臨時の賃金(私傷病手当や退職手当など)
・賞与(1年に3回までの分のみ)
・法令・労働協約の定め以外に基づいて支払われる現物給与
【賃金締切日がある場合】
算定事由発生日の直前の締日からさかのぼる3箇月間で計算します。たとえば休業手当であれば、会社都合による休業の日の直前の締日以前3箇月ということになります。その理由は単純で、計算がしやすいからです。
★平均賃金とは、あくまでも「その人の賃金の平均額」ということであり、「その人が丸一日働いた場合の賃金額」ではないことに留意してください。そこを理解していないと、「えっ、私の平均賃金、こんなに少ないの!」ということになります。
(例)
・月給:200,000円
・暦日数:1月:31日、2月:29日、3月:31日 計91日
この方が「丸一日働いた場合の賃金額」は、月の労働日が20日とすれば、200,000円÷20=10,000円となりますが、平均賃金は暦日数で計算しますので、次の通りとなります。
〇平均賃金=200,000円×3÷91日=6,593.40円
ね、思ったより少なくてビックリしますでしょ。
以上が原則論ですが、日給、時間給、出来高給などの人については、最低保障があるので要注意です。原則の額と比較して額の多い方を採用です。
・最低保障額
算定事由発生日以前3箇月間の賃金総額÷その期間の労働日数×0.6
(例)
・時給1,200円
・暦日数:1月:31日、2月:29日、3月:31日 計91日
・労働日数:1月:10日、2月:10日、3月:3日 計23日
・賃金:1月:96,000円、2月:96,000円、3月:28,800円 計220,800円
〇原則=220,800円÷91日≒2,426.37円
〇最低保障=220,800円÷23日×0.6=5,760円(こちらを採用)
この方の場合だと、最低保障の方がだいぶ額が多いことがわかりますね。労働日数が少ない方ほどこのようになります。