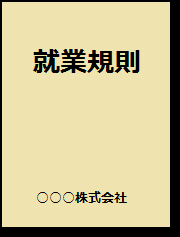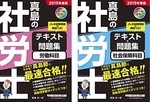〒177-0035 東京都練馬区南田中2-20-38
営業時間:9時~17時
定休日:土日祝祭日
練馬区で就業規則の作成なら 東京労務コンサルティング―社労士事務所―
- 弊事務所は、ブラック企業やモンスター従業員の味方は一切致しません(クリックしてね)!
- モンスター従業員に悩まされる善良かつ健全な企業の味方です!
合格率数パーセントの社労士試験の合格を目指す人たちを指導して合格まで導く仕事ですから、「社労士のみなさんの先生」であるわけです。
したがって、はっきり言って、そこらへんの社労士とは知識のレベルが違いすぎます!一人だけ別世界にいると言っても過言ではありません
完璧な法律の知識を駆使して、最大限あなたのお役に立ちます!
⇒これは、自慢ではなく事実です。真島の知識をあなたに使っていただくためには、謙遜などしている場合ではなく、事実をありのままにお伝えすべきと判断したのです。
※お問い合わせには、すべて真島が直接対応します(それが真島のポリシーです)。
就業規則が会社を強くする!そのワケは?
就業規則が会社を強くする。その理由を考えてみましょう。
就業規則は、会社の法律だから
就業規則は、あなたの会社のルールブックです。国に置き換えれば、ルールブック=法律ですね。そう、「就業規則はあなたの会社の法律である」と表現しても、あながち誤りではないわけです。
仮に、法律がない国を想像してみてください。皆がそれぞれ自分勝手な主張を行い、もめごとが絶えません。それどころか、犯罪が横行してとても人が住めないようなまさに「無法地帯」となってしまうことでしょう。
就業規則がない会社は、法律がない国と同じです。無法地帯に従業員を放り込んでおいて、「みんなで夢を持ってがんばろう!」などといくらきれいごとを言ってみたって、空しいだけです。
しっかりした就業規則(法律)があれば、あなたの会社は組織体として正常に機能します。みなが安心して活力を持って働くことができるので、当然業績が伸びます。
就業規則は、会社の秩序を造るから
①とも通ずるものがありますが、しっかりした就業規則はルールブックとしての役割を果たしますから、秩序を造ります。組織は、それぞれ異なった個性を持った個人の集合体ですから、同じ目的に向けて正常に航海を続けるには、秩序がとても大切です。
就業規則は、不公平感をなくすから
明確なルールのない会社では、処遇に不公平が生じます。「あの人にはあの手当が支給されているのに、どうして私にはないの?」といった具合です。
不公平感は、人からやる気を根こそぎ奪います。従業員間の不公平の払拭は、経営者たる者、いの一番に考え、対策を取るべきものです。
就業規則は、みんなの笑顔を造るから
賞罰の基準が明確となり、また、不公平がなくなれば、従業員は安心して日々の業務に取り組むようになります。笑顔の絶えない明るい職場となるでしょう。暗い職場と明るい職場とでは、どちらがお好きですか?
就業規則は、会社を守るから
人の個性は千差万別ですから、従業員の中には、あなたに牙をむいて来る者もいます。いわゆる労使トラブルの勃発です。トラブルは早期に解決しないと、泥沼に陥りやすいという特徴を持っています。
早期解決に最も役立つのは、言うまでもなく、ルールブックたる就業規則です。就業規則の規定にのっとって粛々と事を処理しましょう。
就業規則がないと何が起こる?!(具体的に)
就業規則のない会社で実際に起きているできごとを、いくつかご紹介しましょう。
試用期間の終了時期でもめる
遅刻や欠勤控除でもめる
「遅刻や欠勤したら給料から引いて良い」。これは、日本の法律の基本的な考え方です。したがって、引くことそのものは構いません。問題は、いくら引くかです。もっと正確に言うと、「どういう計算式で計算して引く額を決めるか」です。つまりは、「賃金控除の計算式はどんななの?」ですね。
びっくりですが、賃金控除の計算式は法律に定めがなく、おのおのの会社が就業規則で決めることになっています(当然ですが、合理的な範囲であることが必要です)。
就業規則がない場合は、この計算式が明確になっていないわけですから、賃金控除自体ができない事態も想定されるわけです。
身だしなみでもめる
就業規則には「服務規律」という項目があり、身だしなみなども掲載することができます。たとえば、「茶髪や派手なマニキュア等は避けること」といった具合です。
就業規則がなければ服務規律もないわけですから、従業員がすごい恰好で出勤して来ても、注意すらできません。
会社都合で有給休暇を付与できない
有給休暇は従業員が申請して取得するものですが、労働基準法は一定の日数につき会社が時季を指定して取得させることを認めています。これを計画的付与といいますが、計画的付与を行うのにも就業規則の根拠が必要です。
変形労働時間制を導入できない
変形労働時間制はあまり耳慣れない制度かもしれません。わかりやすくいえば、「いつも同じ時間働くのではなく、忙しいときは長時間働き、その代わりに暇なときは早く帰って良い制度」です。
曜日や時期によって忙しさが異なる会社にうってつけの制度ですが、これも、導入には就業規則の根拠が必要です。
人事異動ができない
転勤、出向などの人事異動も、就業規則の根拠が必要です。
懲戒解雇ができない
まじめな従業員ばかりとは限らず、時に信じられないことをしでかす者もいます。盗み、傷害、重大な経歴詐称等々。
目に余る場合は他の従業員への示しもあるので懲戒解雇を選択することになりますが、これもまた就業規則の根拠が必要です。すなわち、「以下の行為を行った場合は懲戒解雇とする」との条項が必要ということです。
ひどい従業員をクビにすることすらできない。そんなばかなー!といくら叫んでみても仕方ありません。就業規則をちゃんと整備しておかなかったあなたの責任なのですから。
私どもにおまかせください!
※お問い合わせには、すべて代表の真島が対応します。それが真島のポリシーです。
お問合せ・ご相談はこちら
受付時間:9時~17時
定休日:土日祝祭日
就業規則がない会社に未来はない!
今こそ戦略的就業規則を作成し、ライバル会社に差をつけよう!
私たちは、就業規則の絶対的なプロです!
| 対応エリア | 東京都及びその近県 |
|---|
ブログ(情報提供中!)
(07/15)「真島の社労士」著者による社労士になろうチャンネル
(06/08)奄美の実家が売れてしまいました(2020年6月8日)
(06/08)ユーチューバー(2020年6月8日)
(06/07)労務管理お悩み解決ちゃんねる(Youtube)
お知らせ
1.次のような方からのご依頼はお断りすることがあります。
- 社員を大切にしない方
- 威圧的な方
- All or Nothingな方
- 犯罪行為を強要する方
- 私どもと共に自社を造り上げるとの意識がない方
- その他私どもがお客さまとして不適当と判断した方
2.従業員サイドからのご依頼はお受けしておりません(理由:信義則、利益相反の恐れ、使用者との折衝に立ち会えない)。
3.助成金受給のみを目的とする就業規則作成のご依頼はお受けしておりません。
⇒金額的にも合わないと思いますので(弊事務所の報酬規程はこちら)。その場合はよその社労士事務所へお尋ねください。